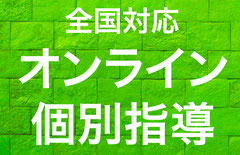医療系 小論文・志望理由書・面接指導塾
医・歯・薬・看護・福祉学部など医療系学部の受験対策

専門のプロ講師が1対1個別指導
様々な医療系学部に対応
- ・医学部
- ・歯学部
- ・薬学部
- ・看護学部
- ・保健学部
- ・福祉学部
- ・栄養学部
- ・理学療法学科
- ・作業療法学科
- ・放射線学科
- ・検査技術学科
- ・助産師養成学校
- ・鍼灸学科
- ・リハビリテーション学科受験
- ・スポーツ健康学科受験
小論文・志望理由・面接対策
関西入試学院は、医学部・歯学部・薬学部・看護学部など医療系学部の小論文・志望理由書・面接受験指導を実施しています。
大学合格のために小論文・志望理由書・面接試験対策をプロ講師が個別指導でサポートします。
医療系では人間性が重視される
医療系学部は医・歯・薬学部をはじめとした多くの専門領域に携わる医療人を育成するための学部です。
尊い人命に接する職業上、学力のみならず患者や家族の気持ちを理解できる人間性が重視されます。受験生は将来医療に従事する者として多くのことを理解しなければなりません。
関西入試学院は医療系学部の進学指導において、長年にわたり多くの実績を重ねてきました。 これからも医療分野を志す受験生の志望校合格をサポートしていきます。
授業では生徒の理解および習熟度を常に確認しながら論理的思考力の定着をはかります。
小論文、志望理由書、面接試験対策において万全の態勢で受験に臨んでいただきたいと思います。
医療系学部の受験対策
医・歯・薬・看護・医療系学部の受験指導に多くの実績をもつプロ講師が徹底指導
医療系学部の受験対策では下記のことが大切です。
総合型選抜・AO入試、学校推薦型選抜・推薦入試、一般入試や指定校入試の出願時に提出する志望理由書では、受験生自身の将来目標を定めることが重要です。特に文章作成では論理的思考力と論理的記述力が必要です。
「自分は将来何がしたいのか」それを自身の言葉で話さなければなりません。また、そのように考える動機や経緯を説明する必要もあります。
そのためには自分自身に向き合い、今までの歩みやこれからの人生に関して深く考える必要があります。その上で、大学での学びの目標を定めなければなりません。
自分の将来について考えて文章にするには、ある程度の時間を要します。夏以降の出願に備えて早めに準備にとりかかることが合格率を上げることにつながります。
関西入試学院では生徒一人ひとりにヒアリングを行いながら、志望の動機や将来目標を合格水準に引き上げるため、しっかりと考えていただきます。
何度も書き直しはあると思いますが、生徒の将来が少しでも良くなることを願っています。生徒の個性を尊重しながら長所を伸ばして、志望校合格に向けて努力して頂きます。
受講生への指導は経験豊富なプロの講師が行います。志望理由や面接の内容は非常に個人的な内容になるため、指導にあたっては生徒を理解し、ヒアリングと対話を重ねることを重視します。
出願までに第三者の客観的な指摘を受けて、思考方法、文章構成や細かいミスにまで改善を行うことが重要です。
考える力を伸ばし、徹底したトレーニングを重ねましょう。おのずと自身の将来目標が明確になってきます。どのように社会に貢献しながら自己実現を果たすべきかを見つけられます。これからの社会はそのように主体的に思考できる人物を求めています。
将来の自分の道を築くために一生懸命努力してください。
●小論文受験対策
試験対策コースの小論文対策講座は、志望分野に応じた小論文課題でトレーニングを行います。受験日から逆算し、集中的に実力を高めることを目的とします。
提出された小論文の改善点を指摘し、修正を重ねながら質の高い文章を書けるように鍛えます。
小論文を書くのが初めての方には、小論文の書き方の基礎から講義を行い、理解を深めていただくことから始めます。
志望校合格のためには、小論文のテーマを数多く演習しておくことが必要です。小論文の構成など重要事項をしっかり理解した後に、多くのテーマで演習して実力を高めなければなりません。
演習量と実力向上は比例しますので、集中してできるだけ多くのテーマで小論文を書くことが合格につながります。
医・歯・薬・看護など医療系学部の受験対策






 関西入試学院
関西入試学院